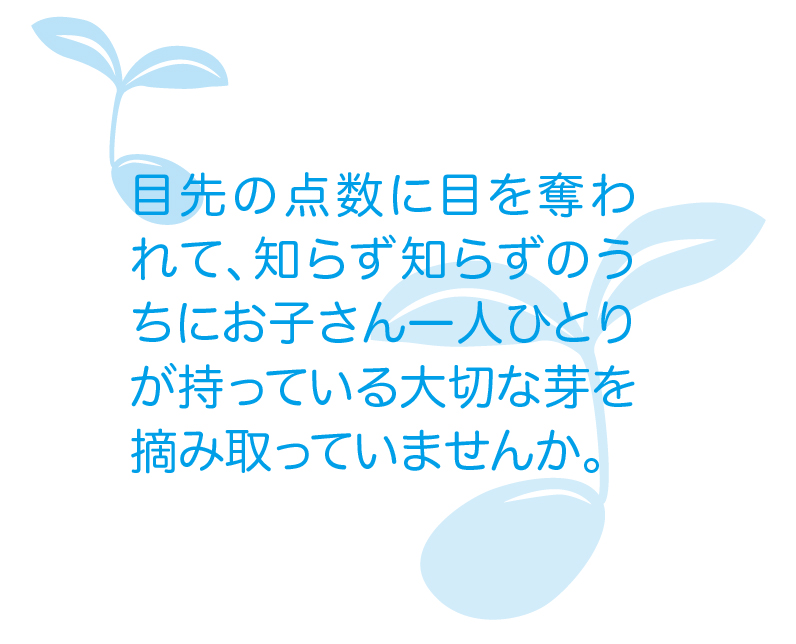
近年、大学生の学力低下が問題となっております。私は、約30年、大学受験のための教育に携わって参りました。実は、この兆候はもっと前からあったのです。言われたことをそのまま繰り返す「能力」を持った「肯定型」の子どもが増えた一方で、言われたことに疑問を抱いたり、自分の頭でもう一度考えようとする「納得型」の子どもが減ってきたという実感を私自身持っておりましたが、予備校の先生や大学の先生からも、本質的に数学の苦手な理系の子がたくさんいるという話を何度となく聞かされてきました。
皆さん、有名私立中学の算数の入試問題を一度やってみて下さい。同僚の数学の先生は「こんな問題を50分やそこらで8割9割の正解率で解け、言われてもちょっと無理。東大・京大の問題やったらできるけどな」と苦笑いしながら言ってました。それほどの「難問」が解ける「優秀」な子どもたちが毎年多くいるはずなのに、なぜ「学力低下」が問題になるのでしょうか。大学生の大半が自ら考えることの苦手な「肯定型」の人間だからです。「難問」を解く「力」をつけるために、問題をパターン化し、解き方という名の「手順」を教え、訓練する、きれいごとを言ってもそれが所謂進学塾の実態です。そこでは、本当の意味での思考力は問われません。本当に理解していなくても理解したような顔をすることでひとをも自分をもいつわり、そのまま解き方をのみ込んでしまうのです。エリート意識のために「わからない」と言うことに抵抗感を持ち、コミュニケーションも十分にとれない子どもたちの姿がここにあります。それでも、効率は悪いながら、勉強量を維持すれば、大学受験まで何とか対応できる子もいます。しかしそこまでです。進学塾と私立中学のイタチゴッコがこういう事態を招いたのかも知れません。
しかし、私たちは中学受験を全否定するつもりはありません。問題は、受験を目的化することにあります。受験を一つの目標あるいは通過点として、そこに向かって努力することには意味があります。
よりレベルの高い問題を解く能力を養うことは、高校受験、大学受験さらにはその先へとつながっていきます。いや、むしろつながるような勉強をしなければならないということです。
私たちは、論理を大切にします。暗記に頼る勉強は非効率になりがちだからです。算数・数学だけを問題にしているのではありません。より根本的には、言語能力が問題となります。正しい言語能力が身についていなければ、論理的な思考はできません。これは、十分な分析力、理解力がないということも意味します。
どの科目を学習するときも思考力が力を発揮します。私たちは、どの科目についても論理に裏打ちされた授業を行います。
高畑A・Tセミナーで体系的学習を実感してください。
周りに流されるのではなく、周りをよく見て、自分の頭で考え、判断できる人間になってほしい。そんな思いを持ってお子さんと向かい合ってまいりました。もう25年になります。
入塾して2ヶ月ほどでやめたいと言い出したものの、ご家族の説得で踏みとどまり、その後高等部を経て、大阪大学理学部に入学したお子さん、中学校のときはいわゆる不登校でしたが、塾での勉強は楽しく続け、大阪府立大学に入って、さらにスキルを身につけるためアメリカの大学院に留学したお子さん、小・中のときはあまり成績は芳しくなかったのですが、コツコツ勉強して西の京高校に入り、そこでそれまでの努力が実を結び、二十数倍の競争率を突破し、兵庫県立大学の理学部に合格したお子さん、などなど、高畑A・Tセミナーには、ここには書ききれないお子さん一人ひとりのさまざまな歴史があります。
子どもの芽を摘むテスト問題
私は大学受験生と接する中で、こうなる前に、もう少し早くからいい教育を受けていれば、もっと伸びただろうにと漠然と思うことがしばしばありました。そして、子どもが学校から持って帰ってくる業者のテスト問題を見てからは、小中からの教育の必要性を強く感じるようになりました。「標準」とか「能力判定」などという名が付いておりますが、その問題の粗雑さによく唖然とさせられました。正しく考える能力を阻害するような問題も散見されます。塾用テキスト、市販のテキストにもその点ではしばしば問題があります。これでは論理的思考力が養えないどころか弊害さえあります。問題を選別することが重要となるわけです。
私たちの教育方針
私たちは、子どもたち一人ひとりが持っている能力を大切にしたいと考えております。テスト攻め、宿題攻めで、目先の成績を上げることだけに汲々とした世間によく見られるような教育方針では、その子どものもっている能力を知らないうちに摘み取ってしまう危険性が付きまといます。どこの大学に行くことになるかは確かに重要な問題です。しかし、私たちは、それだけを問題にしているわけではありません。グローバル化の進行とともにめまぐるしく変化する現代社会、手に入れた知識はどんどん古びていきます。次々に生まれる新たな情報に対応できる柔軟な思考力がなければ、この変化について行けません。私たちは、しなやかな頭脳を持った、真の意味で優秀な人間を育てていきます。
一貫しない文科省の方針
文科省は、先の学習指導要領では「ゆとり教育」を標榜して、理数分野を中心に内容3割、時間2割を削減しました。そして今度は、学力低下を招くとの批判を受け内容の大半を復活させました。しかし、これも中途半端なものになっています。時間が十分に確保されていないのです。現在、さらなる「改革」も叫ばれていますが、結局、文科省の定見のなさを露呈しているだけで、現場は混乱させられるばかりです。
私たちは一貫しています。将来生きていくために必要な思考力の養成も視野に入れ、必要と判断したものは教科書、学校の授業内容に関わりなく教えております。この姿勢は以前からも、そして、これからも変わることはありません。
具体的指導方針
まず第一に、私たちが目指す教育を実現するには一クラスが少人数でなければなりません。一クラスは多くて9名までです。経験的にいって、一人ひとりのお子さんの表情を見ながら授業を進めるためには、それぐらいが限界です。お子さんとのコミュニケーションを取りながら一人一人の理解度や考え方の傾向を把握して行きます。したがって、宿題として出す課題もお子さんによって変わって来る場合があります。
第二に、自分たちが責任を持てないような講師任せの授業は行いません。基本的には、上に述べたような教育理念を持つ私たちが責任を持って授業を行います。私たちは、当然大学受験も視野に入れた上でお子さんの教育を考えております。
第三に、授業はお子さんの理解に合わせて進めていきます。子どもたちの理解が進めば、学校の授業進度とは関わりなくどんどん先へ進めます。子どもたちが、より高度な問題を解いていくことのおもしろさ、考えることの楽しさを実感できるよう指導していきたいと思います。
